
「越境」と呼ばざるをえない善意について
こんにちは、紅龍堂書店の久利生杏奈です。
この文章を書くかどうか、とても悩みました。
特定の一件について述べるものではなく、ここ数年にわたって少しずつ、けれど確実に積み重なってきた違和感や負担について、可能であれば言語化せずに、穏やかな距離を保っていたいという希望があったからです。
ですがこれ以上は静観できないと判断しました。
本記事は、紅龍堂書店という小さな出版レーベルが、スタッフの安全と持続可能な運営のために設けている方針や境界線を、あらためて言葉にしてお伝えするものです。
私たち自身のために、そしてこれから関わる誰かのためにも、「どこまでが共感であり、どこからが越境か」を明確に記しておく必要があると考えました。
齟齬のないように言葉を割いたらどうしても長くなってしまったため、本記事については先に目次を付記しますが、スクロールして読み進めていただいて問題ありません。ご容赦ください。
目次
- 対応に苦慮している越境行為
- 「応援」や「仲間意識」に擬態したバウンダリーの侵害
- トラウマダンピングについて
- 「被害者同士」の錯覚が生む共依存と圧迫
- 曖昧な接近と“友人扱い”の危うさについて
- 記事公開にあたってのお願い
対応に苦慮している越境行為
詳細は後述しますが、具体的には以下のような行為が該当します:
- ご自身の被害体験を長文で一方的に送り付けること
(たとえば、「助けてくれるはず」「無料で話を聞いてくれるはず」といった前提が透けて見えるケースや、「専門家には相談したくない」として、なぜか私たちにだけ過剰な対応を求めてくるケースなど) - 性被害や家庭内暴力を題材とした小説や創作活動を、「版元の応援」という名目で繰り返し送ってくること
(被害や応援を装った自作フィクションの宣伝や売り込み、特にフィクション作品であるにもかかわらず「被害当事者として扱ってほしい」といった要求が伴う場合) - ご自身の近況を一方的に語ったうえで、「私はどうすればいいでしょうか?」など相手の応答を前提とした要求を重ねること
(こうした問いかけには、“責任回避としての顔色伺い”という側面があり、受け手に過度な心理的負荷や判断責任を強いることがあります。私たちは事情を知らず、知る立場にもなく、人生の選択を後押しする役割を担っているわけではありません) - 持ち込み希望であるにもかかわらず、それを明示せず、「応援のつもりで」と曖昧な接近を試みること
(例:クラウドファンディング企画への一方的な便乗、「利益は折半で」といった不当な条件提示、業界関係者を名乗っての“応援”に見せかけた自著のセールス。過去には、スタッフが差別被害で疲弊していた際、「心中お察しします」と書き出されたメールの末尾で、自分の訳書の出版を提案された悪質なマイクロアグレッションもありました) - SNSで数回のコメントのやり取りを経ただけで、プライベート関係や仲間意識を前提に踏み込んでくること
(やりとりの頻度や内容に比して一足飛びに距離を詰めすぎではと感じるケースが多々あり、私たちにとっては「親しいつもりがないのに、親しいと見なされている」と困惑する状況に直面することもあります) - さらにそのような希薄な接点をもとに、「関係者である」「知り合いである」などと公言されること
(特に、第三者に対して関係性を強調する発言が行われると、実態との乖離に困惑せざるをえません。たとえ悪意がなかったとしても、周囲に誤解を与えかねない発信は、関係各所への影響も大きく、対応に苦慮する場面があります) - ごく一部ではありますが、こちらがやんわりと距離を置く姿勢を示すと、突然態度を変え、「紅龍堂書店にこうされた」といった一方的な被害表明や、誤解を招く発信が行われる例も確認されています。正当性や正義を装った言説であっても、それが実質的に他者への攻撃や誹謗に繋がる場合、私たちは深く憂慮せざるをえません。
- 最初はファンのように振る舞いながら、徐々に「悩みを聞きます」「営業できます」「記事書きます」などとアピールして内部に入りこもうとすること
- 新聞や雑誌などの取材依頼に応じた際、記事とは関係のないプライベートな事情を聞き出そうとすること
- あるいは、事前配慮のつもりで「こうした質問はご負担でしょうか?」といった“当事者向けチェックリスト”を提示されたり、「一緒に作りましょう」と持ちかけられること
(善意であることは承知していますが、「これが適切な配慮ですよね」と先回りして同意を求める行為そのものが、大きな負荷となります。ときに配慮の提案というより、配慮のできる自分を印象づけたい意図が見え隠れすることもあり、かえって疲弊を招きます。また、そのような働きかけの前に、まず自らの組織内で加害を防ぐための基本的なガイドラインが設けられているのか、強い疑問を覚える場面もありました)
これらはいずれも、相手の同意や準備を伴わない“接近”であり、状況によっては深刻な越境となりうるものです。
先に明記しておくと、無自覚に境界線を越えてしまった方を責めるつもりはありません。
バウンダリーの習得には経験や技術も必要ですし、誰もが「気をつけて」と言われてすぐに実行できることでもないと、私たちも理解しています。
ただ、弊レーベルには、被害当事者であるスタッフが在籍しています。
大変心苦しいのですが、ここは当事者同士の自助グループではありません。
紅龍堂書店は出版レーベルであり、スタッフには、傷を負ってまで人助けをする理由や義務はありません。
むしろ、直接的に助けることはできないと深く自覚しているからこそ、当事者が直接対峙する必要のない手段として、「書籍」という媒体を選び、活動を続けています。
また、「DM」や「お問い合わせフォーム」は、個人的で密なやり取りをするための手段ではありません。
これはたびたび誤解されてきたことですが、かつて「久利生杏奈」名義をSNSのプロフィールに掲載していた頃は男性からの接触が非常に多く、近年、毒親関連書籍を出版するようになってからは、圧倒的に女性からの“親しげな越境”が増えています。
X(旧Twitter)を始めとする各種SNSアカウントは、プロフィール欄に記載のとおり、全てレーベル公式アカウントです。
基本的にスタッフ全員、場合によっては関係者や弁護士も閲覧します。
果たして、どこまでご理解いただいた上での内容なのかと、戸惑う場面も増えています。
これらの行為がすべて悪意によるものとは限らないとしても、
いま私たちは、明確な境界線が必要な地点に立っている――そのように感じています。
「応援」や「仲間意識」に擬態したバウンダリーの侵害
これまでにも幾度となく、「お手伝いできます」「コラボしませんか」「同じような被害を小説に書いているので読んでほしい」といったご連絡をいただいてきました。そのなかには、「助けたいので連絡先を交換しましょう」「駆けつけられます」「最寄り駅を教えてください」「直接話がしたい」といった申し出も数多くありました。
「自助グループの運営をしています」「NPOとして活動しています」といった肩書きをもとに、連携や共同出版、なぜかクラウドファンディングの利益の5割が欲しいといった支離滅裂な申し出をいただいたこともありました。
善意や公益の名を掲げていたとしても、被害当事者への一方的なアプローチを、私たちは受け入れることができません。
支援の名のもとであっても、また当事者同士であったとしても、他者の境界や尊厳を軽視した接触が許されるわけではありません。
一見すれば親切で熱意ある応援のように見えるかもしれません。
けれど私たちにとっては、それらの多くが、望んでいない“接近”であり、場合によっては深刻なプレッシャーや危険につながりうる越境行為です。
トラウマダンピングについて
特に困っているのが、いわゆる“トラウマダンピング”と呼ばれるような行為です。
トラウマダンピング(Trauma Dumping)とは、自身のつらい経験やトラウマとなっている出来事を、相手の同意や準備を得ることなく、一方的に打ち明けてしまう行為を指します。
必ずしも悪意によるものとは限らず、「話を聞いてほしい」「共感してほしい」といった思いから起こることもありますが、受け手にとっては、突然重い内容を投げかけられることで、心理的な負担や無力感を強いられるケースも少なくありません。
こうした深刻な内容は、本来、支援を前提とした関係性(たとえばカウンセリングや医療機関など)の中で共有されるべきものであり、日常的な交流や初対面の相手に唐突に語られると、信頼関係を損なう結果にもなりかねません。
当レーベルでも、過去の被害体験を長文(中には中編小説に近い分量のものも含まれます)で「読んでください」と送ってくるケースや、私たちの書籍と直接関係のない話題(ご自身の近況、愚痴、判断責任を伴う相談、小説企画の仄めかし、拡散依頼など)を、連続してフォームやDMに投下されるケースが近年急増しています。
SNSを離れていた期間は幸い沈静化していたものの、改訂版のお知らせを出してから再び増加傾向にあります。
「被害者同士」の錯覚が生む共依存と圧迫
悪意によるものではないと分かっていても、受け取る側が疲弊することに変わりはありません。
ときに、「あなたたちは分かってくれるはず」という前提のもとで語られ、「だから私の話を聞いて」「助けて」「評価して」「繋がって」と、さまざまな“要求”が積み重ねられていきます。
「自分も被害者」だという名乗りは、“味方扱いされるべき”というロジックにすり替わりやすく、結果として、断られたら「裏切られた」と逆上するケースも珍しくありません。傷を抱えた人ほど、他人の活動を「自分の居場所」と誤認しやすく、過剰な共犯関係や共依存関係、また承認欲求を求めてしまうという構造もあります。
やむをえない事情も理解しますが、しかしこうした行為は、受け取る側に選択権がない時点で、すでに「共有」や「共感」ではありません。
一方向的な“投げつけ”であり、ときにその善意の顔をした熱量が、私たちの作業や判断を大きく乱すことがあります。
レーベルにとっては、大変心苦しいのですが迷惑行為となりえますし、法的には営業妨害にもなりかねません。
紅龍堂書店は、限られた人員と体力で運営されています。
『毒親絶縁の手引き』のメインライターに至っては、当事者性が高すぎる内容だからこそ、ページ数も、流通方法も、作業時間も限られた「書籍」という形を選び、できるかぎり公共性のある情報発信に心血を注いできたという背景もあります。
極めて限られた体力とリソースの中で活動を続けています。
個別相談に対応することを目的として出版活動をしているわけではありません。そのような専門性や責任を担える立場にもありません。部外者性を強く自覚しているからこそ、書籍では公的・民間の支援先を、類書の中でも屈指と言えるほど多岐にわたってご紹介しています。
それでもなお、専門機関ではなく、私たちを通じた接触が選ばれることに、違和感や戸惑いを覚えることも少なくありません。杞憂であれば幸いですが、仮に「優しそうだから」「断れなさそうだから」「肯定してくれそうだから」といった印象を根拠に接触されているとしたら、それは人間関係における力の非対称性――“断りづらさ”を利用した無意識の圧力になりかねません。
私たちはあくまで本作りの職業人であり、紅龍堂書店としての活動は、出版を中心とした表現と制作の場です。関係者の中には、社会福祉士や精神保健福祉士といった国家資格を有し、日常的に対人援助の現場で働くスタッフもおりますが、それはあくまで個人の職務であり、紅龍堂書店として個別相談をお受けすることは想定しておりません。
専門性があるからといって、私生活や創作の場にまで常時ボランティア的な支援を求められることには限界がありますし、たとえ善意からであっても、それを当然視されることは極めて負荷が大きいものです。
だからこそ、書籍の中では専門機関のご紹介に努めており、その意義と必要性についても繰り返し触れています。
その案内を迂回して私たちに接触されることは、結果としてご自身にとっても、本来受けられるはずの支援の機会を逸してしまう危険がある――このことも、どうか念頭に置いていただけたらと思います。
応援や共感を名乗る行為であっても、無制限に受け入れることはできません。
むしろ、自分の思いや過去を誰かに届けたくなったときこそ、その行為が「一方的な接近になっていないか」を立ち止まって考えていただけたらと思います。
曖昧な接近と“友人扱い”の危うさについて
また特筆すべき事項として、持ち込みをご希望される方のなかには、最初からその意図を明言するのではなく、
「一読者として」や「応援のつもりで」などと、曖昧な関係性のまま接近しようとされる方が一定数いらっしゃいます。
結果として、こちらが一方的に踏み込まれた感覚を覚えることもあり、私たちはそのようなやりとりを「誠実な申し出」としては受け取れません。
これは持ち込みに限らず、ファンのふりをして内部事情を把握しようとしたり、手伝いと称して連絡先交換や直接会うことを要望したり、自身の居場所づくりや承認欲求の充足のために紅龍堂書店を利用しようとする接触も含まれます。
私たちがこれまで築いてきた文脈に土足で上がり込み、利用されるようなことが続くようであれば、私たち自身の活動そのものが立ちゆかなくなります。
紅龍堂書店では、原稿や企画、イベントのご相談について、他のご連絡と同様に、明確な意図をもって、公式にご連絡いただけるようお問い合わせフォームも用意しています。
それにもかかわらず、SNSやコメント欄など、非公式の経路での「友人・仲間」のような接近は、適切な対応ができませんし、逆に信頼を損ねることになりかねません。
なお繰り返しで恐縮ですが、お問い合わせフォームもあくまで業務上の連絡や書籍に関する問い合わせのために設置されたものであり、密な交流や被害相談、個人的な雑談や世間話を行う場ではありません。
フォームからのお問い合わせ内容は、必要に応じてスタッフおよび弁護士と共有され、記録・保管されます。
記事公開にあたってのお願い
私たちは書籍という「媒体」を選び、言葉を託しています。
今この瞬間も、『毒親絶縁の手引き』改訂のために、膨大な校正校閲作業が発生しています。
書き手と読み手が安全な距離を保ちつつ、そこに信頼と、固着しない通過可能な共鳴が生まれるように──そのための表現手段として、出版という営みを選んでいることを、どうかご理解いただけますよう、重ねてお願い申し上げます。
なお本記事を公開することで、「自分のことでは」と不安になる方、失望する方、「応援をやめる」と感じる方、あるいは「応援をやめよう」と正義感の名目で呼びかける方も現れるかもしれません。
このような補足を書かねばならないことには暗澹とした気持ちになりますが、弊レーベル刊行書籍をお読みの方ならばご存知のとおり、他者を攻撃する人は、同じく攻撃を良しとする人同士で群れやすいという傾向があります。
誠に恐縮ではございますが、過度に悪意ある解釈や執拗な行為に対しては、当事者間でのやり取りは控え、必要に応じて弁護士を通じた対応に移行いたします。これはあくまで、スタッフや関係者の安全を守るための事前の方針であり、誰かを脅す意図のものではないことをご理解いただけましたら幸いです。
また、本記事に書いた内容の一部だけを切り取ってSNSに流すことはお控えください(昨今のSNS情勢についてはこちらに記載しています)。
「私のことかも」と確認や謝罪のためにメールを送ることもおやめください。
ここは紅龍堂書店のブログであり、私たち自身の手で運営している表現の場であり、拠点でもあります。
……以上は、当レーベルが考える「正当性」ですが、正しさは、受け取る人が呼吸できる余白があって初めて意味を持ちます。
誰かの胸を押しつぶしながら差し出す「正しさ」とは何なのだろうと自問することを何万回と繰り返してきました。
この記事は、決してあなたを糾弾するためのものではないのだということを、最後に改めてお伝えさせてください。
お読みいただきありがとうございました。
紅龍堂書店
久利生杏奈
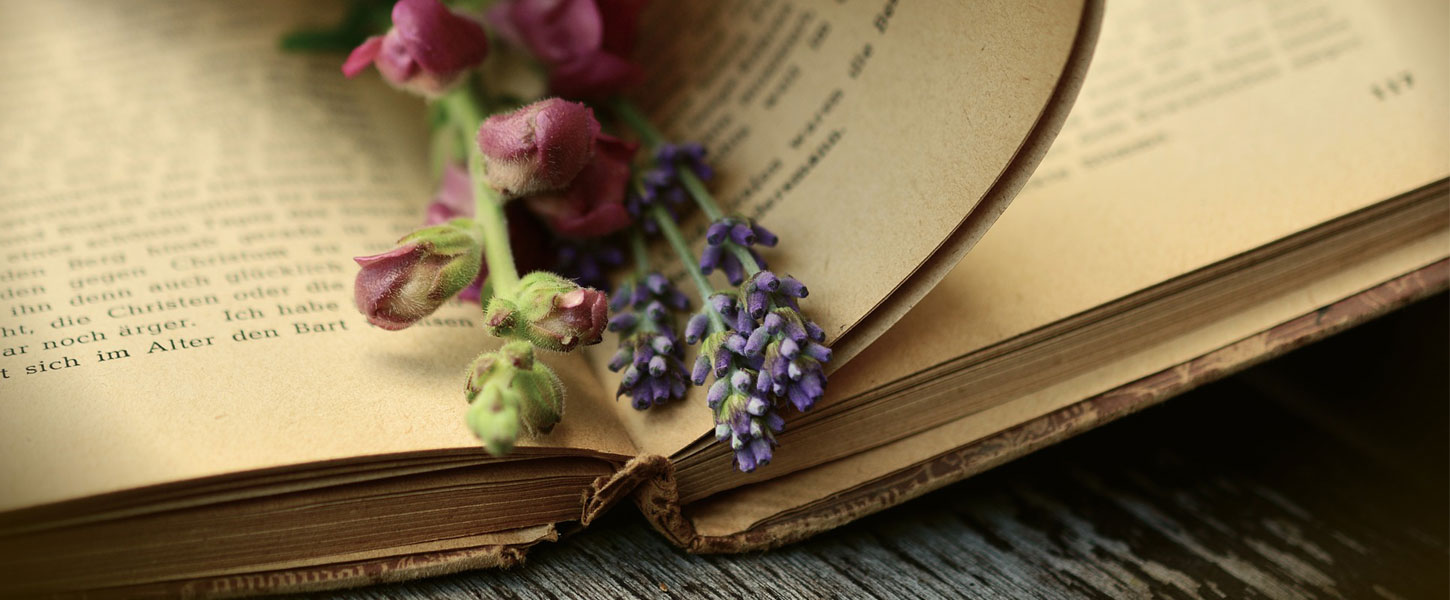

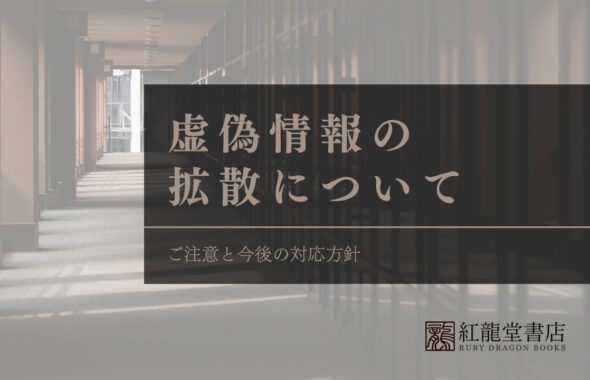

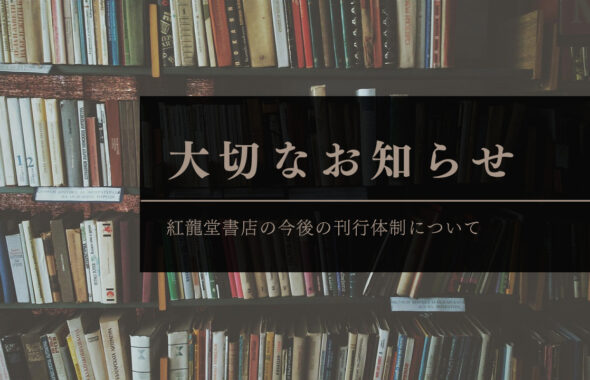
この記事へのコメントはありません。