
参政党の憲法草案を読んで、添乗員が思うこと
準国家資格保持者として、また観光地で暮らす者として、どうしても書いておきたいことがあり長文になります。
普段は表に出ない裏方スタッフの一人ですが、この場を借ります。
紅龍堂書店の「物語」のファンの方はご容赦ください。
観光地の現場から考える
知らない方も多いと思うので少しだけ自己紹介すると、私は総合旅程管理主任者です(一部の方にはGoToトラベル反対署名でお世話になりました)。いわゆる海外旅行添乗員の有資格者ですが、主に携わってきたのは富士登山ツアーの添乗です。富士山五合目から上に登り、ご来光を見たいというお客様を、国籍性別年齢問わず千人以上ご案内してきました。
だからまず、これを書くと憤る人、また傷つく外国ルーツの方が多いことは百も承知の上で、「外国人観光客ってちょっと迷惑だな」と感じる人が多い事情は、理解しているつもりです。
「日本人だって迷惑かけてるじゃないか」「外国人だけを悪く言うのは偏見だ」、こちらも重々承知です。その上で、どうか最後まで読んでいただきたいです。
まず観光地で起きていること。
地元民が「神域」として大切に守っている場所で、「外国人」が自撮り棒を振り回す。ゴミ箱の場所が分からないため、「外国人」が空き缶やペットボトルを置いていく。山では、雨具もヘッドランプも持たず、半袖・サンダルで登ろうとする「外国人」。日本語も英語も全く通じず、ツアーからはぐれて迷子になる「外国人」。金剛杖の焼き印(スタンプ)を集めようと、列から外れてしまう「外国人」。「絶対に遅れないでください」と何回念を押しても、毎回集合に遅れる「外国人」。
誇張ではなく、散々見てきました。
自分で言うのもなんですが、自力下山が不可能になった観光客を避難させた経験は、そこらで排外主義を叫んでいる人たちよりよほど多いと思います。その上で。
私自身は接客中に、外国人観光客の方に対して嫌な気持ちになったことは一度もありません。
言えば伝わるからです。
べつに英語が流暢でなくても、理屈を伝えればそれで済みます。
「It’s dangerous.」の一言で、すっと納得してくれる方がほとんどです。
でも多くの日本人は、迷惑行為を目にしても、ただ遠巻きに眺めているだけです。
心の内で何か思っても、燻らせるだけで言葉にしない。誰かが「迷惑だ」と言い出してくれるのを待っている。目を逸らして、見て見ぬふりをして、「自分が注意してトラブルになったら嫌」「空気を乱すのは恥ずかしい」と口を閉ざす。
その消極的姿勢を“和”や“謙虚さ”だと美化している。
もちろん、争いを避ける姿勢や空気を読む感受性は、日本文化の中で長く培われてきた大切な美徳です。
とくに保守的な価値観を大切にする方の中には、「その場で声を荒げること」が無礼であるとお考えの方も少なくないでしょう。
けれど、その“美徳”が機能するのは、全員が同じ前提を共有している社会においてだけです。
「自分が我慢しているのだから、周囲も察するべき」というのは、言わば日本という島国のローカルルールですから、その前提が通じない相手に、どう対応するか。
新しい知恵や選択肢が必要だと考えませんか。
「察して」で世界は動かない
日本人って、日本人同士の迷惑行為にも口を挟まない人がほとんどですよね。
旅行業に関して言えば、バスの遅延で添乗員を怒鳴りつける高齢者男性。事故渋滞とかどうしようもないですがめちゃくちゃ多いです。でも車内で添乗員を助けてくれる人は見たことがありません。
こういうことを書くと、「それは年齢層の問題では?」「老害が」と言う人が必ず出てきますが、コロナ禍で地方医療リソースが圧迫されもう限界だったとき、何の躊躇もなく押し寄せていた人たちは老若男女を問いませんでした。「病床が無いんです」「地元民が死にます」とどれだけ説明してもお構いなしでした。彼らは「コロナは風邪だ」とノーマスクでやってきました。
もちろん、日本人全体がそうだと言いたいわけではありません。
あれから5年も経つのに、こんな無名の若造の言葉を、今なお真摯に読んでくれるあなたもいます。
ただ、日本では「和を以て貴しとなす」という価値観がとても強いために、表立って注意することが“波風を立てる行為”として敬遠される文化的な傾向があるのは否めません。
そのせいか、とくに観光や接客の現場では、「理屈を説明しても理解しようとしない人」や「納得のいかないことでも怒鳴って通そうとする人」が一定数いるのも事実です。
それに比べれば――という話ではありますが――外国人観光客の多くは、言えば通じるんです。
もちろん全員がそうとは言いません。でも、建前や慣習でなく、理屈で話せば届く場面が多いという実感が確かにあります。
自分が、たまたまそういう恵まれた場面に多く立ち会ってきただけかもしれません。
けれど、日本一の標高を誇る霊峰・富士で、千人以上の登山客を案内してきた中で得たこの感覚は、少なくとも机上では得られない現場の一つの「声」だと受け取っていただければと思います。
沈黙は「肯定」を意味する
オーバーツーリズムに辟易しているのなら、まず観光客向けの多言語の案内やサイン、アナウンスの整備が急務です。ゴミの分別ルール、立ち入り禁止エリアの表示、それだけで防げるトラブルは山ほどあります。
あとはシンプルに、嫌なら意思表明することです。
流暢じゃなくてもいいから、できる範囲で伝える努力をすること。
それが、言葉を共有しない人との接点では、驚くほどに効果的なことは多いです。
黙っていては伝わりません。
分からないんです。
その場で誰も何も言わなければ、相手は「問題なかった」としか受け取りようがないのです。
もちろん、「黙る」という選択もあります。
でもそれは、“衝突を避けるための沈黙”であると同時に、“改善の機会を手放す”ことです。
これって日本人同士でも同じですよね。あなたの職場の上司はどうですか? 取引先は? 黙っていても何もかも通じます?
もし本当に、外国人観光客に改善してほしいことがあるのだとしたら、何も言わずに背を向けるだけでは、変えることは難しいです。
……とはいえ、たぶんここまで読んでも首を傾げている人にとっては、そういうことじゃないのだと思います。
「ゴミの分別を伝える」「禁止エリアの表示を工夫する」――そんな対症療法的な努力ではなく、そもそも、そこに“異質な存在”がいること自体が、もう耐えがたい。
貴重なリソースを、外国人“対策”に割くことそのものが嫌だと感じている方も、正直、少なくないのだと思います。
「差別」なのか、生活の摩擦なのか
案内や整備などのインフラ以前に、「自分とは異なる外見の人が歩いているだけで怖い」。
「前は電車で座れたのに、今は観光客が多くて座れない」。
「見知らぬ言語が飛び交っているだけで疲れる」。
そういう、塵が積もり続けた結果の「うんざり」もあるんじゃないでしょうか。
こういうことを書くと、今度はリベラル寄りの人、特に社会資本に富んだ教養ある人ほど怒ると思うのですが、しかし日常生活の小さな感情の蓄積を「差別だ」と切って捨てるのも、私は雑じゃないかなと思います。
日本では、通勤ラッシュの電車の利用者は圧倒的にサラリーマンの方ですよね。
労働者の自分がくたくたに疲れてつり革につかまって、押し潰されそうになって足が浮いてる時に、デカい旅行ケース持った富裕層が目の前のシートに座って、知らない言語で楽しそうに大声で喋り続けてたら、けっこうキツくないですか。
そこで「日本へようこそ」って思え、寛大でいろというのは、それはそれでまた、想像力の欠如した感情の強要ではないかとも思います。
それでも「鎖国」では生きていけない
閉鎖的で息苦しい空気のなか、日々ぎりぎりの生活を送っている人がこれほど多い社会において、「共通言語がない人を怖い」と感じるのは、構造的に当然の帰結だと思います。
「外国人が多すぎて疲れる」「見知らぬ言語が飛び交うのが怖い」――そうした感情の芽生えそのものを完全に禁止・排除することは不可能ですし、一歩間違えれば全体主義の兆候でもあります。
ですが、「怖い」という感情だけをもとに、他者の排除や制限を正当化しはじめるのならば、それは政治の暴力です。
加えて、私たちの暮らしがどれほど外国の資本・技術・労働力・情報に依存しているか、事実に目を背けて理想「だけ」を掲げることは、私たち自身にとっても極めて危ういことだとも思います。
たとえば、「外国人は出て行け」とイーロン・マスクが所有するX(旧Twitter)上で叫ぶ。
その投稿データは、米政府の関係機関が監視・保存する対象になっている可能性が高いことをご存じでしょうか。
スマートフォンは Apple(米国)や Samsung(韓国)製が多く、検索エンジンは Google(米国)。SNSは Instagram(米国)や X(米国)。そして、こうしてやりとりされるデータの多くは AWS(アマゾン・ウェブ・サービス)や Microsoft Azure に保管されています。
“日本製だけ”で人生を完結させることは、もはや現実的ではありません。
労働現場も同様です。
コンビニ、農業、介護、建設――外国人労働者の力がなければ、社会が回らない領域がすでに多数あります。
そんな中で、「外国人を減らせ」「女が子どもを産めばよい」「天皇は側室を持てばいい」「ニートが働けば移民はいらない」「戦争になったらゲームプレイヤーにドローン攻撃をさせよう」などと語る政党が、少なからぬ支持を集めているという事実には、正直なところ、深い懸念を抱かざるをえません。
参政党の話です。
一つ一つの発言の真偽はググってください。ああ、Googleって外国資本の会社ですが。
参政党が宗教的世界観に基づいた政治理念を持つ団体であること、そしてその影響力が無党派層や若年層にまで及んでいることも、改めて指摘しておきます。
補足すると、「日本を日本人(?)の手に」「日本を舐めるな」といった主張そのものが悪だと言うつもりはありません。
DNA検査をすれば日本が単一民族国家だなんて幻想もいいところだと一瞬で分かりますが、個人の信条で科学を信じないと仰るなら、それも尊重されるべき自由の一つです。
ただ、2025年という時代を生きる有権者として、どうしても問いたいことがあります。
AIと量子コンピュータが標準となる時代を、“日本人だけ”で乗り切れると、本気で思っているのでしょうか。
AI全盛時代の「鎖国」は国家を自滅させる
現在、世界中で開発が進められているAIモデル、たとえばChatGPTやGeminiは、主に英語を中心とした情報を学習しています。次点が中国語。日本語はその構文の特殊性や情報量の少なさゆえ、AIにとってはあくまでマイナー言語のひとつに過ぎません。
つまり、日本語だけで情報を得ている人間は、AIがもたらす知識や恩恵から取り残される構造に、時代としてはすでに突入しているわけです。
これは教育や経済だけの問題ではありません。
まず医療。
英語で日々アップデートされていく世界標準の臨床研究や論文を、十分に読めないまま診療にあたる――それがどんなリスクを含んでいるか想像してみてください。
工学、金融、教育政策も同じです。
量子コンピュータの導入によって、世界中の金融市場や軍事戦略はコンマ秒単位で変わるようになります。そんな中で、「役所言葉」と前例主義しか通じない政治体制で、果たして何が守れるでしょうか。
中国は2016年に量子通信衛星「墨子号」を打ち上げ、軍事転用を含む国家戦略をすでに進めています。
アメリカは、AIと量子暗号・量子計算を用いたミサイル防衛構想を国家レベルで実装しつつあります。
その間、日本では「神話教育を必修に」やら、「家族観の回復を」やら、内向きの議論ばかりが先行し、現場の技術者たちは次々と海外に流出しています。
そして私たちは、AIにも量子コンピュータにも、自前の基盤を持たないまま、利用者として依存する国になりつつあります。
そのような状況で、「外国人を排除しよう」「日本人だけでやり抜こう」と語ることに、果たしてどれほどの実効性があるのでしょうか。
想像したくありませんが、敢えて喩えるならこうです。
戦争が起きたとします。
相手のミサイルが、量子コンピュータの演算によって最適化された弾道で撃ち込まれてきます。
そのとき、私たちは“精神論”や“神話的な価値観”で立ち向かうのでしょうか。
参政党が「有効性」を主張するように、クールジャパンのドローン操作を信じる? プロゲーマーを量子演算に対抗する人殺し部隊に? なるほど。
戦争といえば、「日本も核武装するしかない」と勇ましく煽る声もよく聞くようになりました。
言っている本人は真剣なのでしょうが、楽観主義だなと感じざるをえません。
今の日本は世界有数の原発大国です。原発事故から十年以上経ってもなお、廃炉技術すら確立できず、汚染水処理にさえ国際的な非難を受けている。それでも「安全性は大丈夫」と言いながら再稼働を進める一方で、その原発の上に核兵器まで積む?
自己矛盾を受け入れられる胆力にだけは脱帽します。
軍事バランスを口にするなら、それこそ量子技術やサイバー戦、経済制裁や情報戦が主軸になりつつある現代において、核兵器を“切り札”として扱う発想そのものが時代錯誤ではないでしょうか。
防衛や外交を語るなら、まずは今ある技術とリスク管理を直視する力こそが、最も重要な「国防」ではないですか。神話の時代に戻るのではなくて。
科学と情報を武器とする国家に囲まれているという現実の中で、日本語だけ・日本人だけで世界と競争し続けようとすること自体が、すでに成立しない幻想です。
懐かしさや「日本らしさ」を愛することは否定しません。
ですが、その感覚を優先した政策判断が、もし国家の未来を大きく誤らせるとしたら、代償を背負うのは、私たち次の世代です。
「日本を舐めるな」?
本当にそう思うのなら、日本こそが、世界を舐めずに現実に目を向けるべきではないですか。
そもそも「円安」をなんだと思ってる?
では、もう一歩だけ足元を見てみましょう。
私たちの日常生活で最もダイレクトに「世界」と接続されている経済現象――それが、円安です。
2022年以降の急激な円安により、日本は“世界で最も安くて安全な国”になりました。
その結果、外国人観光客が押し寄せ、街の飲食店や観光地では「インバウンド向け」に特化した価格設定や接客が増えているわけです。
「旅行に行っても落ち着けない」「観光地が外国人だらけで嫌になる」という冒頭の話に繋がります。
ここで、しがない旅行添乗員として問いたいと思います。
円安って、いったい誰の責任で、どんな目的のもとに起こっているのでしょうか。
多くの人が見落としがちですが、円安は「自然に起きた現象」ではありません。これは日本政府と日本銀行の選択――つまりは「日本経済の延命」のために、意図的に起こされた政策の帰結です。超低金利政策の継続、国債の大量発行、それによる円の価値の相対的低下。
対して、米国をはじめとする主要国はインフレ抑制のために金利を引き上げ、通貨価値を守ってきました。
結果、何が起きたか。
世界の投資マネーは「円」を見限り、利回りの高い外貨資産に向かい、通貨の実質購買力は下がり続けています。
私たちは、これまでよりもはるかに高い物価を日常的に支払うようになり、輸入品やエネルギー価格の上昇が家計を直撃しています。
そして、もうひとつの重要な副作用が、冒頭でも触れた「人の流入」です。
円安によって、日本は「安くて安全で、割安な労働力が手に入る国」として国際的な魅力を高め、訪日外国人や外国人労働者の流入が加速しているわけです。
「外国人が増えすぎて困る」「日本人の雇用が奪われている」と言うなら、まず「円安」という仕組みの意味を考えるべきだとは思いませんか。
こうも言い換えられるかもしれません。
円安を支持し、実質賃金が下がり、外国資本に依存し、国際競争力を失っている今の日本を「このままでいい」と思っている政党は、果たして誰のための政党なのでしょうか。
参政党を始めとする一部政党は「売国は許さない」と叫びますが、現実の経済構造や国際通貨システムについて、まともな提案を一つでもしていますか?
どうやって「日本を日本人の手に取り戻す」と叫んでいます?
国会では与党寄りの姿勢を見せつつ、経済政策の大枠には異を唱えない。
円安をつくった構造には加担しつつ、その結果として人が動いてきたことだけを非難するという、論理的に整合しない立場をとっている。
これは、自分たちが支持してきた政治のツケを、他者に転嫁している構図ではないでしょうか。
もう一度、富士霊峰の現場を見てきた登山添乗員として、改めて問います。
迷惑なのは「外国人」ですか?
「女を家庭に戻せば少子化が解決」するわけないだろう
考えるべきは、私たち自身の購買力を取り戻すことです。
「外国人が悪い」「日本を取り戻せ」と感情的に叫ぶ前に、本当に考えるべきなのは次の問いです。
どうすれば、この国で暮らす私たち自身の購買力を取り戻せるのか。
どうすれば、円の価値が安く見積もられずに済むのか。
本当に「日本を取り戻したい」のなら、やるべきは外国人排除ではなく、円の価値、そして社会の生産性と技術競争力を、地に足ついた方法で取り戻すことです。
そのために必要なのは、「伝統」でも「美しい家族像」でも「愛国心」でもなく、冷静な経済戦略と、未来を見据えた国家設計です。
しかし参政党の憲法草案には、こんな文言があります。
「婚姻は、男女の結合を基礎とし、夫婦の氏を同じくすることを要する」
「義務教育には神話・修身・武道・政治参加を必修とする」
男女の「結合」という表現がまずグロテスクで気持ち悪いですね。
ここから読み取れる設計思想として、「男は稼ぎ、女は家庭を守る」という、戦前モデルの再現を志向していることはまず間違いないでしょう。詳細はググ――いえ、読んでみてください。
私自身は、天皇の臣民として生きろと憲法に強要されるのは嫌だなと思います。
もちろん、家族を大切にしたい、母親が子どもと過ごせる時間を増やしたい、そう思う人がいるのは当然ですし、尊重されるべきことです。
しかし、「女性を家庭に戻すことで国が再生する」と政治家が考えているなら、それは時代錯誤どころか、経済的・社会的な自殺です。
もう一度、現実を見てみましょう。
今、世界の先進国では、研究者、エンジニア、医療従事者などあらゆる分野で、女性を含めた全層の人材確保と活用に国家ぐるみで取り組んでいます。
つまりこれからの時代、競争力を取り戻すために必要なのは、高度な教育と技能を持つ人口の「絶対数」です。
にもかかわらず、日本では「女は家庭に入れ」「家父長制を取り戻せ」と政治が語り出している。人口の半数を意図的にイノベーションから隔絶しようとしている。
これでは人材不足が解消するどころか、人材を潰す愚策です。
もちろん、「専業主婦を選ぶ自由」や「家庭を大事にしたい価値観」は守られるべきです。
けれど、それは個人の選択として保障されるべきであり、国家が押しつけるモデルではありません。
女性を「出産と育児のための存在」として位置づけ直す発想は、社会の構成員ではなく“産む機械”と見なす卑しい思想です。
そんな国に、未来を託したい人が増えると思いますか?
女性が安心して働き、暮らし、学び、子を育てられる社会を作ることこそが、出生率を回復させ、イノベーションを支え、国の持続性を担保する最も確実な道です。
国家は“愛国的な家族像”ではなく、「すべての人が能力を発揮できる構造」を作らねばなりません。
それを拒んだ国家は、これからの時代、良く見積もって緩やかに、最悪の場合、急速に滅んでいくのではないでしょうか。
「宗教的価値観」が政治を乗っ取るとき、何が起こるのか
参政党の問題の根幹は、「保守」や「伝統」ではありません。
もっと深いところにあるのは、宗教的価値観を政治に持ち込み、国家運営に適用しようとしている構図です。
もちろん、信仰やスピリチュアルな価値観そのものを否定するわけではありません。
けれどそれは、個人の内面の自由として保障されるものであって、政策の根拠になるものではないはずです。以下は一例ですが、
- 波動水・波動米・高額の霊的商品を売りつける人物が中心にいる
- 謎の「免疫活性」や「オーガニック信仰」が教育や医療政策に持ち込まれる(セリアック病やグルテン不耐症のことを言いたいなら分かるのですが、「メロンパンを一つ食べて翌日死んだ人たちを何人も見た」は、ちょっと……)
- 「神話教育」「修身」「武道」が憲法に書き込まれる
- 指導者への異議は信仰心の欠如として否定される(秘書の方は自殺してますよね)
──さすがに引きます。
ここまで来ると、宗教の皮をかぶったポスト近代型の支配構造です。
“感情”や“共鳴”を重視し、科学的反証や議論を排し、異論を「信仰の外」として排除する。
合理性ではなく「空気」と「ノリ」で政策が決まる社会が、まともに機能するとは私には思えません。
国家が宗教と手を結んだとき、歴史がどう動いたかを、私たちは知っているはずです。
それでも、その道を「なんとなく」支持してしまうならば、想像力と認識の放棄だと言わざるをえません。
未来を担う世代が、何を学び、何を手放し、どこに希望を持てるか。
それを左右するのが、いま私たちが選ぶ「政治」ではないでしょうか。
懐かしさと怒りの声ばかりが大きくなっている今だからこそ、誰かが見つけた「答え」に飛びつくのではなく、ぬるま湯のようにあたたかい「真実」に縋るのではなく、今ある現実的な選択肢の中から、自分の手で未来を選びたい。
選べるだけの克己心を、私たち日本人は、まだ持っているはずです。
読んでいただいてありがとうございました。
投票、行ってきます。
裏方スタッフ@投票日は三連休中日より平日希望。
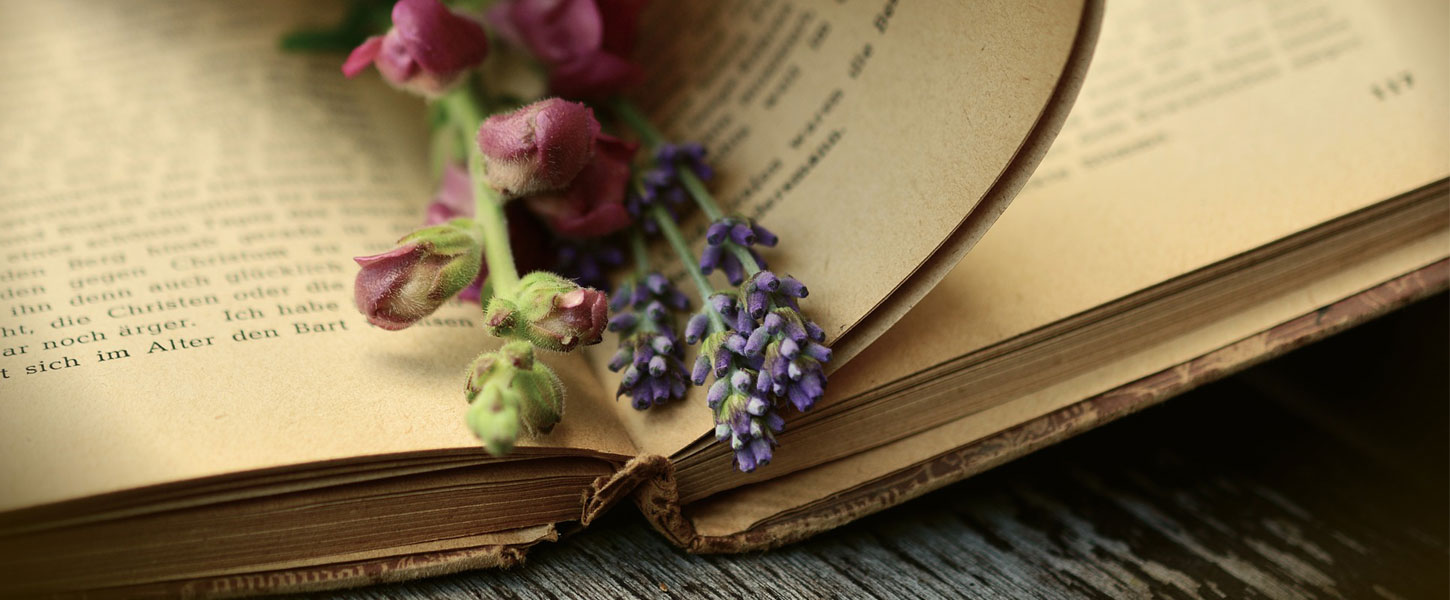


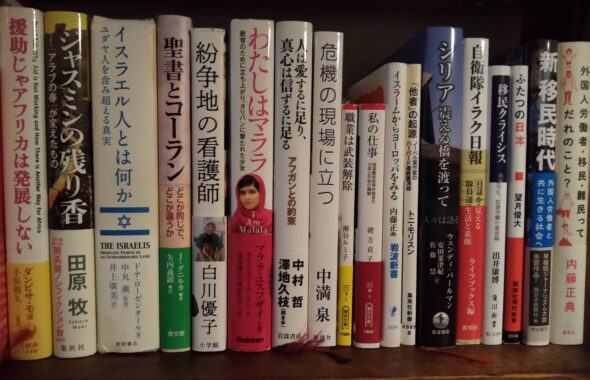



この記事へのコメントはありません。