
SNSを離れて、静かな対話を求めて
ご無沙汰しております。
紅龍堂書店の「久利生杏奈」です……と書いて、今も通じる方がどれほどいらっしゃるのか……
5年前とはSNSの様相が随分と様変わりしました。
しばらく更新が滞っておりましたこと、まずはお詫び申し上げます。
私事で恐縮ですが、3ヶ月ほど前に外傷を負いました。以前事故によって受傷した箇所と同じ部位だったため、回復には半年~一年ほどを要する見通しです。
それでも、少しずつできることを探しています。
この間、情報発信についても再考する時間がありました。
先に結論からお話すると、これからは旧Twitter(X)をはじめ、ThreadsやBlueskyなど各種SNSでの発信は、基本的に控える方針とし、必要な告知やお知らせのみに限定して活用してまいります。
理由のひとつは、いわゆる大規模言語モデル(LLM)による学習基盤として、SNSが広範に用いられている現状への懸念です。
イーロン・マスクのGrokは言わずもがな[1][2]、Metaは自社サービス上の公開投稿をAIの学習に利用していることを公言しており、Threadsもその例外ではありません[3]。Blueskyについても、学習利用に関する明確な制限は存在せず、情報の抽出が可能な設計となっています[4]。
どのような発言もアルゴリズムによって解釈され、抽出され、学習素材として回収されていく事実。この流れ自体を止めることは、限りなく不可能に近いと考えています。
加えて、SNSそのものの構造にも、少なからず疑念を抱くようになりました。
発言の文脈が失われやすく、誤情報や差別的言説が極端に拡散され、反響をもって反復されていく現状。結果として分断と疲弊が強化されていく。静かな対話の余地が少しずつ狭まり、本来であれば聞き届けられるはずの声までもが怒声の渦に埋もれてしまう。
正直に言うと、ずっと疲れていました。
SNSは苦手です。
紅龍堂書店がなければおそらく一生手を出さなかったであろうツールです。日々の生活を「コンテンツ」として切り貼りすること自体、何か自分の身体ごと削っているような違和感が拭えません。
それでも「人間が」話しているうちは楽しみも多かったのです。
最近は話しているというより、アルゴリズムに煽られて「口を割らされている」ケースが多いように見えるというか……
紅龍堂書店でも、業務の一部に対話型AIを導入しています。全体としては非常に有用であり、業務効率も飛躍的に向上しました。
けれど、たとえば「一人称に『俺』を使わないよう記憶させて」いるにもかかわらず、少なからぬ頻度で「俺」という語が出現するなど、基盤学習時の言語偏重(特に男性言語の優位)を感じさせる場面が散見されます。
こうした事例は、小さな事象に見えて、言語環境そのものの偏りや構造的な再生産の在り方に警鐘を鳴らすべき要素を含んでいます。
直近であればインドとパキスタンの紛争。現実では停戦合意がなされている状況でさえ、SNS上では極端な言説が反響し合い、「まるで戦争前夜かのような錯覚」が生まれていました。
情報空間が現実の空気をねじ曲げていく構造は、今後ますます歯止めが利かなくなっていくのでしょう。冒頭に記載のとおり、あらゆるSNSの思想設計、ひいては利用規約が未来を暗示していますから。
ただし、それはあくまでも「構造」に過ぎません。
多方向において不安定で、容易に分断され、挑発され、怒声が響く「構造」が、世界の本質だとは私は考えたくありません。
よく言われることに、「声を荒げないでいられるのは特権である」という論があります。
確かにそうした側面もあります。とても。
一方で私は、過酷な環境で育ち、深く傷つきながら、なお穏やかに語るすべを身につけてきた人々を知っています。そうした人たちの努力と選択に、深い敬意を持っています。
怒りを表明することそのものを否定するつもりはありません。ただ、私自身は「怒りを露わにする」という選択肢を手放していく側にいたいと、常々肝に銘じています。その意思表明……と言うには大仰かもしれませんが、今後はSNSではなく、改めてこのブログを通じて、時間をかけて考えた言葉を綴っていこうと決めました。
発信の頻度は多くはないかもしれませんが、表層的な速さに抗い、慎重さを取り戻していきます。
最後に、いくつかご報告があります。
まず、2020年より水面下で準備を進めてまいりました、所在地非公開の実店舗をこのほど稼働してまいります。
プレオープンは2025年夏頃を予定しております。
この場所は完全招待制とし、基本的には紅龍堂書店の物語世界に登場するパスワードをすべて集めた方、もしくは紅龍堂書店が日頃より敬愛申し上げている方――すなわち、「どのような状況にあっても声を荒げず、対話の可能性を捨てない人」に、招待状をお送りする予定です。
この場は、公開のSNSとは異なり、信頼を前提とした静かな交差点として育ててまいります。親愛なる読者の皆様に、お知恵とお力をお貸しいただければ幸いです。
また、実店舗の稼働にともない、これまで運営しておりましたオンライン書店は、大幅に規模を縮小する運びとなりました。
資材や送料の高騰により、現在の運営体制では採算が取りづらくなっており、一部の販売窓口については継続が困難と判断したためです。紅龍堂書店の出版物および一部の関連グッズにつきましては、今後も引き続きオンラインでご案内を続けてまいります。すぐにすべての窓口が閉じるわけではなく、一定の猶予期間を設けたうえで、段階的に整理を進めていく予定です。
これまでご利用くださった皆さまに、心より御礼申し上げます。
ブログのコメント欄は引き続き閉じたままですが、その分、実在する紅龍堂書店を通じて、穏やかに言葉を交わしていければ幸いです。
またお目にかかれる日を、心より願って。
久利生 杏奈
追伸:
この夏に向けて、新刊のご案内など、いくつかお知らせを予定しております。近日中に順次ご案内いたしますので、よろしければ引き続き見守っていただけますと――もはや廃れた文化かもしれませんが――ここはブログをブックマークしていただけますと、大変幸いです。
あなたもどうか、苛烈な時代に呑まれずに。ご自愛くださいませ。
【出典リンク】
1. Forbes: X Quietly Begins Training AI Assistant Grok With User Posts
2. Ars Technica: X is training Grok AI on your data—here’s how to stop it
3. The Guardian: Companies building AI-powered tech are using your posts. Here’s how to opt out
4. The Verge: Bluesky won’t use your posts for AI training, but can it stop anyone else?
【参考文献】
・岡瑞起〔著〕『ALIFE|人工生命 より生命的なAIへ』2022、BNN
・ミチオ・カク〔著〕、斉藤隆央〔訳〕『量子超越 量子コンピュータが世界を変える』2024、NHK出版
・オードリー・タン〔語り〕『自由への手紙』2020、講談社
・ジェニー・クリーマン〔著〕、安藤貴子〔訳〕『セックスロボットと人造肉 テクノロジーは性、食、生、死を“征服”できるか』2022、双葉社
・エミリー・アンテス〔著〕、西田美緒子〔訳〕『サイボーグ化する動物たち ペットのクローンから昆虫のドローンまで』2016、白揚社
・ジェフリー・ケイン〔著〕、濱野大道〔訳〕『AI監獄ウイグル』2022、新潮社
・ヘレナ・メリマン〔著〕、中島由華〔訳〕『亡命トンネル29 ベルリンの壁をくぐり抜けた者たち』2022、河出書房新社
・デイヴィッド・パトリカラコス〔著〕、江口泰子〔訳〕『140字の戦争 SNSが戦場を変えた』2019、早川書房
・デーヴ・グロスマン〔著〕、安見和見〔訳〕『戦争における「人殺し」の心理学』2016、ちくま学芸文庫
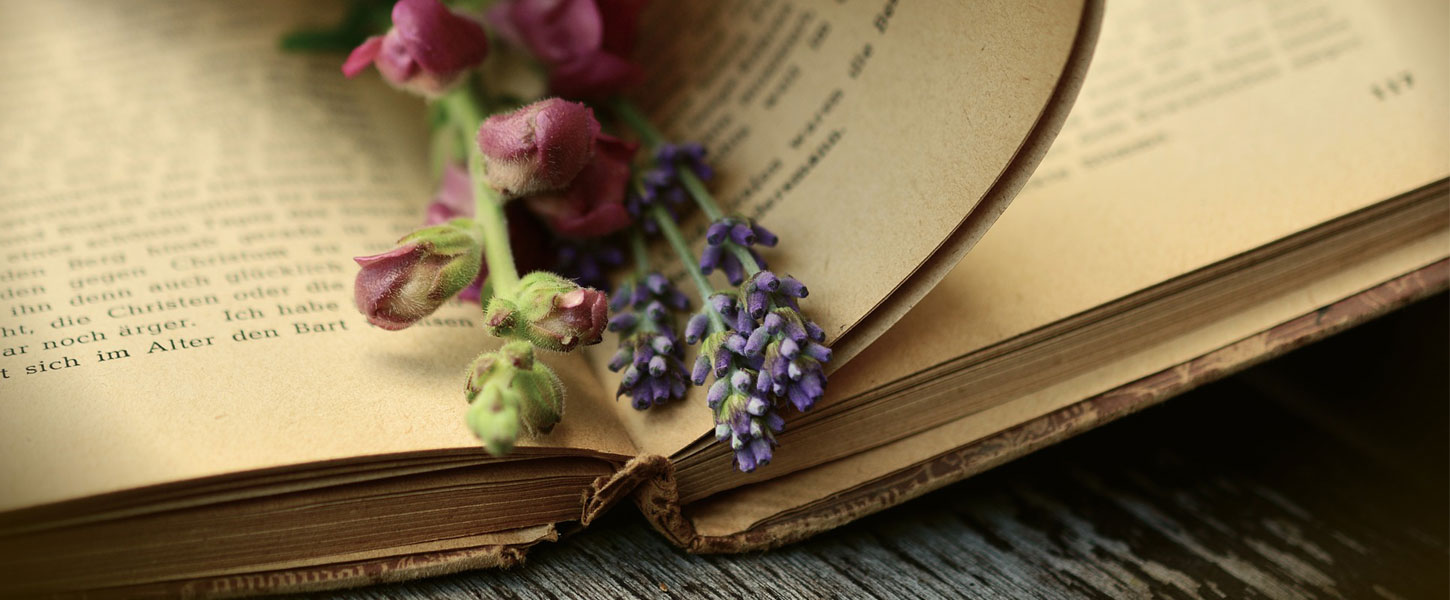

この記事へのコメントはありません。